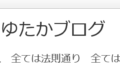日本の年中行事・歳時記
年中行事とは、毎年特定の時期ごとに行われる行事の総称です。民俗学の説明では「日本の自然風土、四季の特色を生かした暮らし方、生活の知恵、生活習慣など様々なものが長い年月にわたって蓄積されてできた日本の暮らしの文化」だそうです。
伝統的な年中行事の多くは、普段の食事と異なる「行事食」(=季節ごとの年中行事やお祝いのときに、その季節にあった旬の食材が使われた特別な食事)を食べて健康を願うのが習わしになっています。
こんにちでは、日本古来のもの、古くに海外から入ってきて土着化したものだけでなく、明治以降に海外から入ってきて商業主義と結びついたりして浸透してきているものも含めて年中行事と呼ばれているようです。
かつての私にとっての年中行事:“そういうもの”
私は、「お正月」は別格として、小さな子どもの頃は、「節分」「ひな祭り」、「端午の節句」、「七夕」、「お盆」は家庭で行っていました。まだ小さな子どもでしたから、親がするのでそういうものだと理解していただけでした。
社会人になってからは、「お正月」は別格として、毎年欠かさず継続して行っているものは、特にありません。この記事を書いている今日は2月3日、今年(2023年)の「節分」の日ですが、この日に恵方巻を食べたことは過去に何回かありますが、現在は特に関心はありません。
年中行事との付き合い方の変化:きっかけは、選択肢の中から絞り込む決め手としての活用
さて、「選択の自由」があること自体は重要なことですが、選択肢が多すぎて一つに絞るのに時間がかかり過ぎてしまったり、絞り切れずに悩んだあげく結局決められないで先送りするという経験は誰しもあると思います。
私は、コロナ禍が始まって以降、家庭料理をするようになったのですが、「今日はぜひこの献立を作って食べてみたい」というハッキリした意欲が一年365日毎日あるわけではありません。今日の献立は何にしようか? 今日はこれにすると決心する決め手は何なのか? と献立を決めるのに悩んで時間がかかってしまうことが多々あります。
こんな具合で家庭料理の献立を思案する場面で、ある時ふと思いついたのです。「そうだ。今日は年中行事の「○○の日」なので、その行事食を献立に加えよう」と。例えば、2023年は2月5日(日)が「初午の日」なのでその行事食の稲荷寿司をその日に食べようとか、夏に鰻の蒲焼を食べる日は夏土用の丑の日にしよう、という具合です。
近所に散歩に出かける場面でも同様です。私の自宅近辺には手頃な散歩コースがいくつかあるのですが、「6月30日は「夏越の大祓」の日で、近所の○○神社では「茅の輪神事」をするそうなので、茅の輪くぐりをしに立ち寄ろう」ということでその日の散歩コースを決める、という具合です。
ただし、年中行事をなんでも取り入れるのではなく、自分の好みに応じて取捨選択しています。
現在の私にとっての年中行事:“日常のささやかな彩”
上述しましたように、私にとっては、選択肢を絞り込む決め手の一つとして活用するようになった年中行事ですが、自分の好みに応じて取り込むことにした年中行事については、そのいわれや意味を調べて、感謝や祈願をしながら楽しむようにしています。
今では、日常生活のマンネリ化を防止する一助となっていますし、暮らしにささやかな彩を添えることに役立っています。