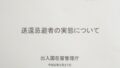はじめに
5月27日は、藤原定家(注1)が小倉山の山荘の障子に和歌を全部で百首貼って完成させたと考えられている日が1235年(文暦2年・嘉禎元年)5月27日であることにちなんで制定された記念日です。
当初は、『小倉山荘色紙和歌』、『小倉色紙』などと呼ばれていたそうですが、天智天皇(注2)から順徳天皇(注3)の時代までの百人の歌人の歌を一首ずつ取り上げて集めたことから、そして、その場所が小倉の山荘だったことにちなんで、後になって『小倉百人一首』という呼び方が定着したということです。
最近では、「小倉」を付けずに単に『百人一首』と呼ばれることもあります。
(注1)平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての公家・歌人
(注2)飛鳥時代の第38代天皇。645年の大化の改新の中大兄皇子として有名。
(注3)父である後鳥羽上皇の討幕計画に参画し、それに備えるために承久3年(1221年)譲位して上皇となったが、倒幕が失敗し(承久の乱)、鎌倉幕府によって佐渡へ配流された。
夏が近いので夏を詠んだ首を紹介
「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山」
「夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月宿るらむ」
「ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば ただ有明の 月ぞ残れる」
「風そよぐ 楢の小川の 夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりけり」
古典落語のネタで使われて有名なものは………
「瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ」
「ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」
かるた形式、そして競技かるた
安土桃山時代に百人一首がカルタ形式になって、その後、江戸時代に、印刷技術が発達したことで、和歌の上句を読み上げて下句が書かれた札をとる「歌がるた」が作られ、庶民にも百人一首が楽しまれるようになったそうです。
「競技かるた」とは、百人一首の「上の句」を読んで「下の句」のかるたをとる競技で、個人戦としては、男女別の予選を勝ち抜いた男性挑戦者が前年の名人(男性)と対戦して名人・準名人を決める「名人位決定戦」と、女性挑戦者が前年のクイーンと対戦してクイーン・準クイーンを決める「クイーン位決定戦」が、毎年1月の第1土曜日に近江神宮(注4)の近江勧学館で開催されています。
(注4)滋賀県大津市所在。御祭神の天智天皇の御製「秋の田の かりほの庵の とまをあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」が『百人一首』の一首目になっていることにちなんで、近江神宮が “かるたの聖地” になった、とされています。