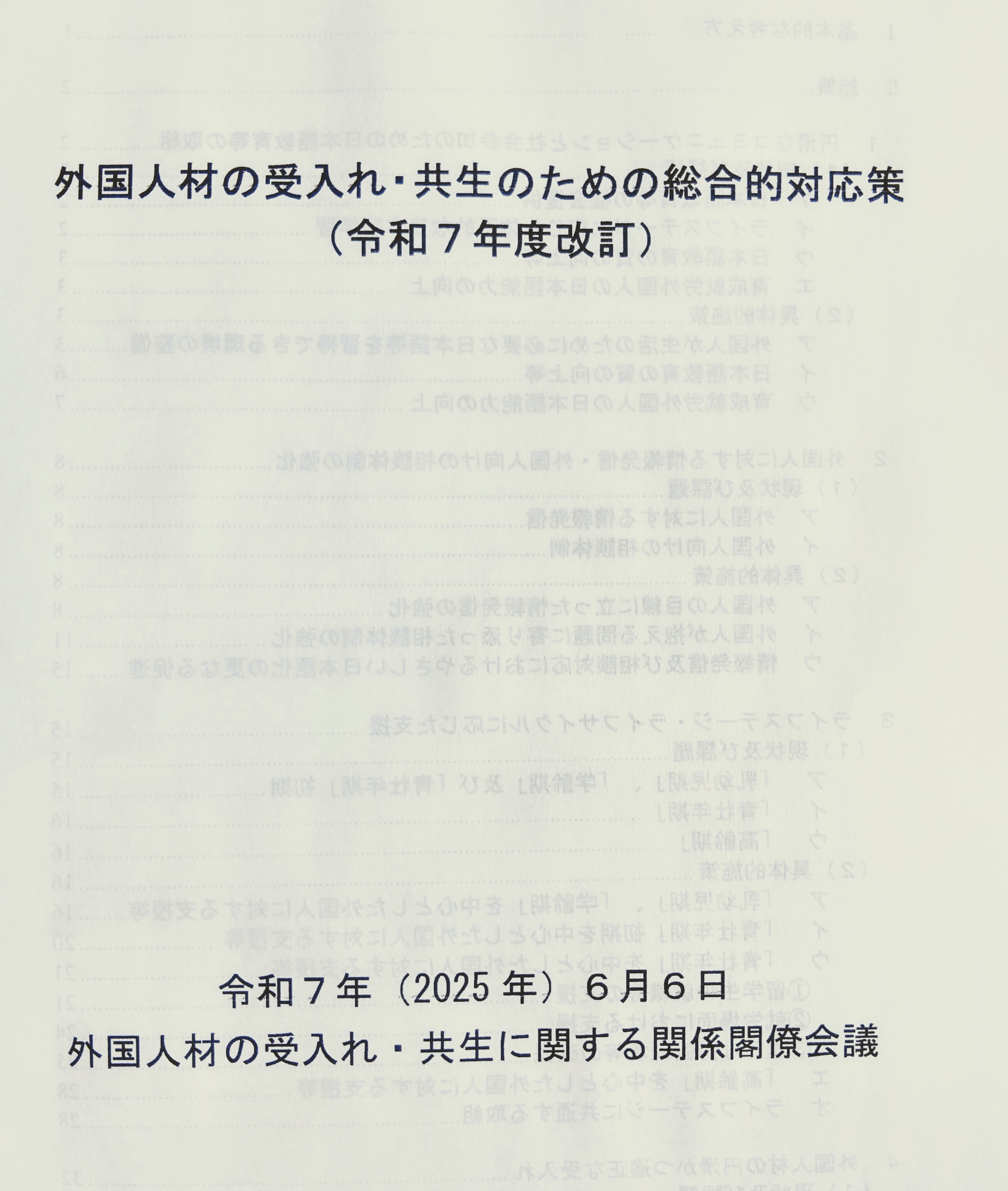【はじめに】「共生社会」は本当に国民の総意なのか?
2025年6月、『外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和7年度改訂)』が、政府の関係閣僚会議によって正式に決定されました。この総合的対応策は、今後も日本に居住する外国人の数が増加していくことを前提に、その受け入れ環境を整備し、日本人と外国人が「共生」する社会を目指すと謳っています。
しかし、ここで一つ、大変重要な視点が欠けています。それは、「なぜ日本が本格的な移民国家にならなければならないのか」という問いに対する十分な議論と、国民の信任を得るプロセスです。
本記事では、今回の『総合的対応策』の中身と、それが抱える致命的な問題点を明らかにし、移民政策という国家の根幹に関わる方針が、なぜ国民的議論なしに進められているのかを問い直します。
「外国人との共生社会」──美しい言葉の裏にある現実
政府が掲げる「外国人との共生社会」とは、日本人と外国人が互いに尊重し合い、安全・安心に暮らすことができる社会を指します。言葉の響きは美しく、反対するのが難しい理想にも思えます。しかし、その実現の前提となるのが「相当数の外国人を恒常的に受け入れる=移民国家化」であることは、ほとんど語られていません。
2024年末時点で、日本に在留する外国人の総数は約377万人に達し、過去最高を更新しています(出典:出入国在留管理庁「令和6年6月発表・令和5年末現在の在留外国人数」)。また、2024年10月末時点での外国人労働者数は約230万人と、こちらも過去最高となっています(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ【令和6年1月26日公表】」)。
そして政府は今後、さらにその数が増加することを「前提」として対策を講じています。
つまり、「共生社会の実現」とは、少数の外国人との一時的な共存ではなく、大量の外国人を日本社会の一員として制度的に組み込む、すなわち「移民政策の推進」に他なりません。
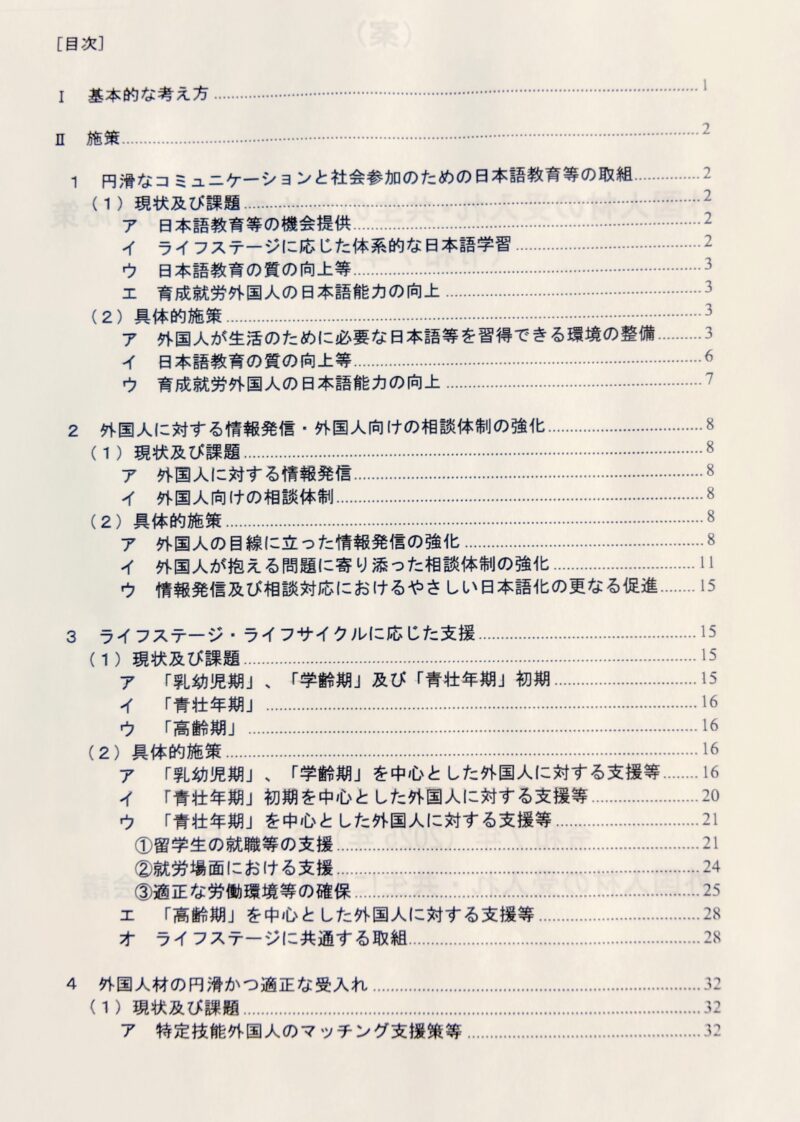
議論はあった──しかし、それで足りるのか?
「外国人との共生社会の実現」に向けた政府の取り組みが、すべて「国民的議論を経ていない」と断じることは、厳密には正確ではありません。これまでにも、国会での審議や関係有識者による意見聴取、一部の報道機関による特集、そしてパブリックコメントなど、一定の議論の場が設けられてきたことは事実です。
しかしながら、それらの「議論」は、国民全体がこの重大なテーマについて十分に認識し、自らの意志を反映できるレベルに達していたとは言い難いのが現実です。
たとえば、移民国家となるか否かというような国の根幹に関わる政策について、総選挙で主要な争点として明確に提示され、各政党が正面から立場を示し、主権者である国民が判断を下す機会はほとんどありませんでした。
しかも、政府はこれまでの政策のなかで、「我が国は移民政策を採っていない」という立場を繰り返し表明してきました。事実、2025年6月の総合的対応策でも「移民」という言葉は慎重に避けられています。
しかし、実態としては、外国人労働者の長期・定着化を促し、在留資格の拡大や永住資格の取得要件緩和など、まさに移民政策の本質に沿った内容が次々と進められてきました。これに対してなお「移民政策ではない」と強弁する政府の姿勢は、主権者たる国民に対する説明責任を果たしているとは到底言えません。
このような、実質的な「移民政策」の推進を覆い隠し、「あくまで一時的・限定的な外国人材の受け入れである」と見せかける姿勢は、有権者の判断を誤らせる、極めて重大な背信行為であると断じざるを得ません。
本来であれば、移民国家化を進めるかどうかは、選挙によって主権者の信を問うべき重大政策の一つです。にもかかわらず、それを明確に示すことなく、「共生社会の実現」という耳あたりの良い言葉で包み込みながら既成事実を積み重ねるやり方は、民主主義の根幹を揺るがすものです。
私たちは、「議論はされた」という事実のみに満足せず、それが真に主権者の意思を反映する過程であったかどうかを、今こそ問い直す必要があります。
なぜ国民的議論が必要なのか?──その理由を整理する
では、なぜこの政策に国民的議論が必要なのでしょうか? その理由は少なくとも以下の通りです。
① 主権者は国民である
日本国憲法第1条にあるように、「主権は国民に存する」。つまり、国家の基本方針を決めるのは主権者である私たち国民であり、政府はその委任を受けて政策を執行する立場にあります。移民政策のように社会構造を根底から変えるような方針は、主権者の判断なしには進めるべきではありません。
② 長期的影響の大きさ
人口動態、労働市場、社会保障、治安、文化的同質性など、あらゆる側面で影響が長期に及びます。しかも一度進めてしまえば、後戻りは難しくなります。だからこそ、慎重かつ広範な議論が必要です。
③ 現在の「共生社会」政策は説明不足
現時点での「共生社会」政策では、「なぜ」「どのように」日本が移民国家になるべきなのかという論拠が十分に示されているとは言えません。多くの場合、「人手不足の深刻化」に対応するためという説明がなされますが、それだけで国家のあり方を根本から変える政策を正当化することはできません。
「人手不足が深刻だから」という理由だけで、外国人を長期的に大量に受け入れ、日本社会に定着させていくという方針を、国民的合意もないまま既定路線として進めていくのは、あまりにも拙速で一方的です。
「受け入れ環境の整備」という美名の下で進む既成事実化
政府は「受け入れ環境の整備」という言葉を使い、外国人が快適に暮らせる制度・支援策を次々と導入しています。教育、医療、通訳、住居支援、雇用支援、差別防止、自治体への財政支援など、外国人向け施策は広範囲に及びます。
これらは人道的には理解できる面もありますが、問題はそれが「移民政策の実質的推進」であること、そしてそれが「国民の合意なきままに、既成事実化」されている点です。
こうして気づけば「日本社会の構成員の一部は、制度的に常に外国人を含む」ことが当然となり、なし崩し的に「移民国家」が現実化していくのです。
私たちができること──民主主義を守る行動を
こうした流れに対して、私たち国民ができることは何でしょうか。
まず大切なのは、「知ること」「問うこと」「声を上げること」です。
この政策が国会でどのように扱われているのか?
各政党は移民政策に対してどういうスタンスをとっているのか?
自治体の取り組みはどうか?
そして次の選挙で、移民政策や外国人政策をきちんと争点として掲げる候補者・政党がいるかを見極め、判断材料とする必要があります。
また、SNSやブログ、地域の集まりなどで意見を表明することも重要です。小さな声が集まれば、政策の方向性を変えることも可能です。
【おわりに】移民国家化は「決定事項」ではない──今こそ、主権者の声を届けよう
「外国人との共生社会の実現」は、日本の将来にとってきわめて重要なテーマです。しかし、それが「いつの間にか決まっていた」ような形で進められていいはずがありません。
移民国家になるかどうか。それは、国民自身が選ぶべき道です。
民主主義を守るために、今こそ私たち一人ひとりが「声を上げる」ことが求められています。
その声が、国の未来を左右するのです。