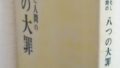「性悪説(せいあくせつ)」とは
「性悪説(せいあくせつ)」とは、古代中国の戦国時代末期の哲学者・思想家の荀子という人物が唱えた人間の本性についての主張です。
「人の性(せい)は悪なり、その善なるものは偽(ぎ)なり」(『荀子』(注1)性悪篇より)から来ています。
(注1)荀子の教えが中国の前漢王朝の末期にまとめられ、その書名が唐王朝の時代に『荀子』と改められています。
世間で誤解されて使われる場合の「性悪説(せいあくせつ)」の意味
誤用される場合は大抵、「人は生まれながらにしてワルである」という意味や、だから「相手を性悪(しょうワル)、悪人であると疑って、用心して接する」という文脈のようです。
「人の性(せい)は悪なり、その善なるものは偽(ぎ)なり」の正しい意味
「性悪説」における「人の性(せい)は悪なり、その善なるものは偽(ぎ)なり」という言葉が、誤解を招いているようです。
「人の性(せい)は悪なり」の「悪」は、罪や悪事という意味ではなく、「人間は未熟で、社会的な規範に沿って行動する能力を自然には持ち合わせていない」という意味に近い、ということです。
ここで言う「善なるもの」は、後天的に学習等を通じて習得される行為や習慣のことです。
「その善なるものは偽(ぎ)なり」の「偽」は、「“人”+“為す”」=「人間の行為」を指すものであって、偽物や嘘を意味するものではありません。
まとめれば、「人間は生まれ持った本性が非常に弱い存在であって、その善なるものは後天的につくられたものである」という意味です。
荀子の「性悪説」は、人間は生まれつき利益を好む心、他人を妬み憎む心、声色を好む心がある非常に弱い存在であるという観点に立っていて、だからこそ、後天的に立派な人間(人格者)になるためには、規範による教えと社会の規範や作法による指導、本人の努力が必要である、と唱えています。
補足
ちなみに、孟子(注2)が唱えた「性善説」の本来の意味は「人は本来善であるから、努力を惜しまなければ、立派な人間(人格者)になることができる」だそうです。
比較すると、「性善説」は「悪い人にならないために努力と勉学に勤しむべきである」と説き、「性悪説」は「善い人になるために努力と勉学に勤しむべきである」と説いているものであって、どちらも「善い人になるには努力と勉学が必要である」旨主張している点で共通しています。
(注2)古代中国の戦国時代の儒学者・思想家。