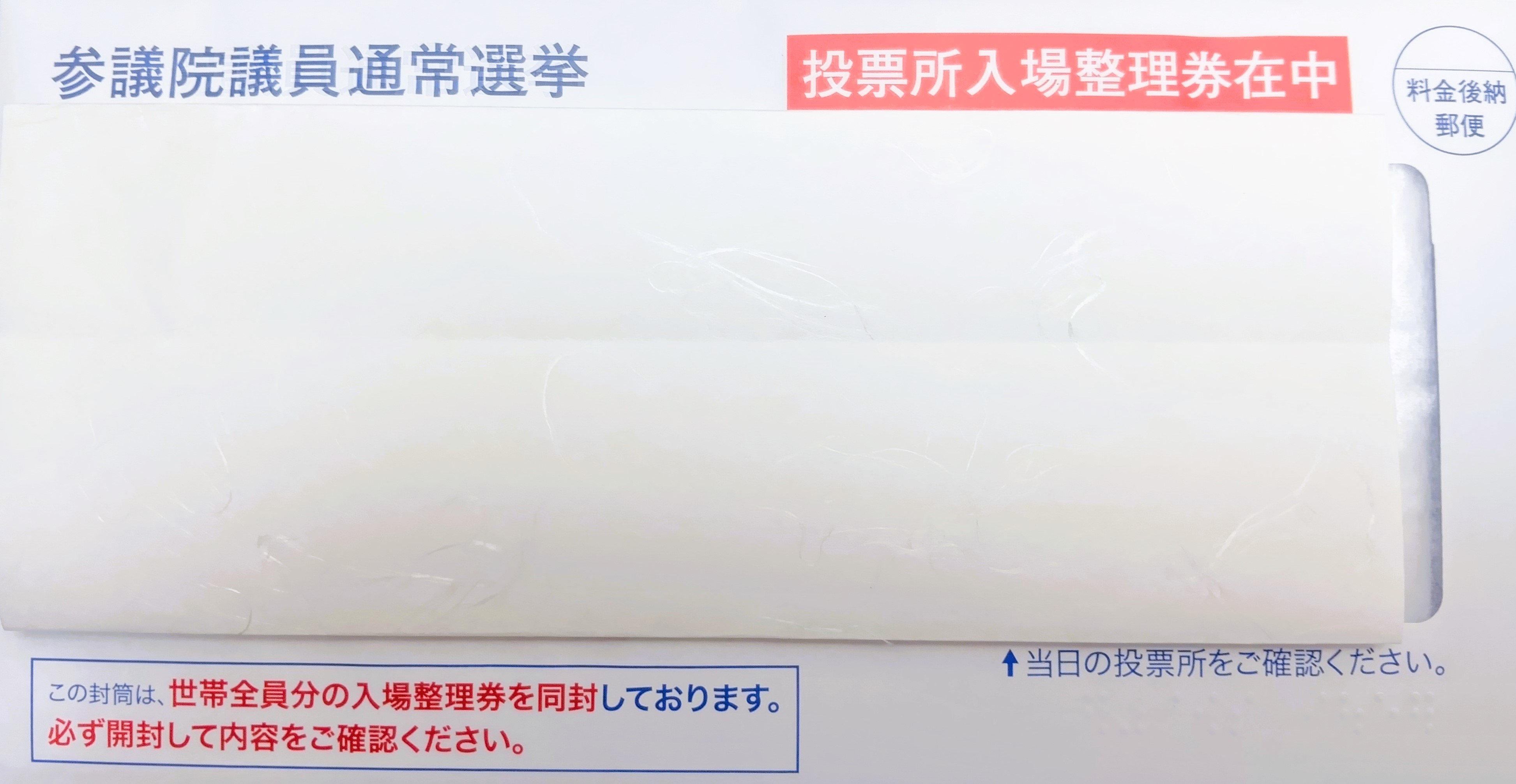はじめに──政治のニュースに、ため息をついていませんか?
「どうせ政治なんて変わらない」「誰がやっても同じでしょ」「もう期待するだけ無駄だよ」。
最近、こんな言葉を耳にする機会が増えていないでしょうか。政治家による不祥事や説明責任の不在、身内に甘く国民に厳しい政策決定──目を覆いたくなるようなニュースが続けば、誰しも無力感を覚えるのは当然のことです。
そんな中、2025年7月20日には参議院議員選挙の投票日が迫っています。
「また選挙か」「誰に入れていいかわからない」と思う人もいるかもしれませんが、この機会をただやり過ごしてしまうのか、それとも「変えるための一歩」として活かすのか。それによって、これからの日本の未来は大きく異なってきます。
たしかに、現状に不満を抱くのは自然なことです。ただし、そこから目を背け、無関心や諦めに流されてしまえば、社会はさらに悪化していきます。なぜなら、民主主義社会において政治を動かすのは、政治家だけではなく、私たち有権者一人ひとりの意識だからです。
本記事では、混迷する現代日本の政治に対して、悲観するだけでなく前向きに向き合っていくための心構えと考え方を整理してみたいと思います。
なぜ私たちは政治に疲れるのか?
政治に対する「幻滅」や「疲労感」は、単なる気分の問題ではありません。それには複数の要因が関係しています。
①報道のインパクトに振り回される
マスコミ報道の多くは、不祥事や対立、スキャンダルに焦点を当てがちです。その方が数字が取れるからです。しかし、そうした報道ばかり目にしていると、「政治=腐敗や裏切り」といったイメージが固定化されてしまいます。
②実感の乏しさ
国会で審議される政策や法案が、私たちの生活にどう関係するのかが見えにくいことも、政治への関心を遠ざける原因です。「どうせ自分には関係ない」と思う気持ちは、こうした実感の希薄さから来ているのかもしれません。
③無力感と失望感
「誰に投票しても同じ」「一票で何が変わるのか」と感じる有権者は少なくありません。しかし、それこそが、政治を特定の人たちに “明け渡してしまう” ことにつながります。
民主主義における「私たち」の力
私たちはしばしば「政治家がだらしない」と批判しますが、実は政治家の質は、有権者の質を映す鏡ともいえます。民主主義は、国民が「主権者」として、社会の方向性を決定する制度です。
●「選挙」はゴールではなくスタート
選挙の投票は、たしかに大切な政治参加の機会ですが、それだけがすべてではありません。政治は選挙のときだけのものではなく、私たちの生活のすぐそばに常に存在しています。日々の中で、どんな意識を持ち、どんな行動を取るか──そこにも政治参加の要素があるのです。
●「棄権」は反対意見ではない
よく、「投票に行かないのもひとつの意思表示だ」という意見を耳にしますが、それは極めて危うい誤解です。選挙を棄権することは、「このままでいい」と黙って現状を受け入れることと同じです。
つまり、不満を抱いている政治に対して、白紙委任状を差し出すような愚かな行為にもなりかねません。
声を上げなければ、誰にも届きません。投票に行くことは、最も基本的で、確実に自分の意思を政治に反映させる手段なのです。
情報リテラシーを高める
現代は「情報過多」の時代です。テレビ、新聞、SNS、YouTubeなど、あらゆるところから政治的な話題が流れ込んできます。しかし、それらの情報には誤解を招くものや偏った見方も多く含まれています。
●情報を鵜呑みにしない
「誰が言っているのか」「どの立場からの主張なのか」を意識するだけでも、見え方は変わります。複数の情報源を照らし合わせ、冷静に比較検討する姿勢が重要です。
●異なる意見に耳を傾ける
自分と異なる立場の人を敵視するのではなく、まずは理解しようとする態度が社会を健全にします。「分断」ではなく「対話」を重ねることが、政治への信頼回復の第一歩です。
良い政治家を選ぶには?
日本の政治に「期待できない」と感じる人が増えている背景には、候補者を見極めるための情報が少ない、あるいは興味が持てないという現実もあります。
●候補者を「顔」や「政党」だけで判断しない
ポスターやテレビでよく見るから、SNSで話題だから……。それだけで候補者を選んでしまっては危険です。その人の政策内容・実績・人柄を、できる範囲で調べてみましょう。
●小さな選挙ほど重要
国政選挙よりも、地方選挙の方が生活に密接な政策に関わります。町のインフラ、福祉、教育など、自分たちの暮らしに直結する施策を動かすのは、むしろ自治体の議員や首長です。
日常生活における「前向きな政治参加」
政治とは、選挙の日だけのものではありません。私たちは日常のなかでも政治と関わっています。
●地元議員に声を届ける
陳情や意見送付は、難しいことではありません。メールや手紙、SNSなどを通じて、市議・県議・区議に自分の意見を伝えることは、立派な政治参加です。
●家庭や職場で「政治を語る」
政治の話題をタブー視しないことも大切です。友人や家族と意見を交わすなかで、自分の考えが深まり、より良い社会像を描くことができます。
おわりに──希望を捨てないという選択
日本の政治に、課題が山積しているのは事実です。しかし、それを変えられる可能性があるのも、また私たち自身です。
一人の力では何も変えられないように思えるかもしれません。けれども、その「一人」が集まって、社会を形づくっているのです。
「どうせ変わらない」と嘆く前に、「では、自分にできることは何か」と考えてみる。
それが、賢い有権者としての第一歩です。
政治は、あなたの日常のすぐそばにあります。
あきらめず、見捨てず、関わり続けましょう。
未来を変えるのは、今のあなたや私、皆さんの一人一人の意識なのです。