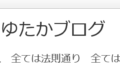桜(ソメイヨシノ)の木はなぜ川岸に多いのか?
私たちの国・日本は、全国各地に桜(主にソメイヨシノ)の木が植えられていて、そのおかげで、桜の名所の桜はもちろん見事ですが、名もない近所の桜の木で十分お花見を楽しめるのがいいですね。
ちなみに、桜の木がなぜ特に川岸に多いのでしょうか?
一説によると、江戸時代、幕府8代将軍徳川吉宗が、治水工事の一環として隅田川の堤防に花見用の桜の木を植えたことがきっかけとなっているそうです。
当時、江戸を流れる隅田川は、長雨ですぐに水かさが増して水害を及ぼすということが多々あったそうで、その対策の一環として川沿いに桜の木を植えたのだそうです。桜の木を植えると当然多くの人が集まります。そうすると地面が踏み固められて天然の堤防の役割を果たすようになり、驚くほど水害が減ったそうなのです。
予祝としてのお花見
話を戻して、例年、あなたの地元の近所の桜はいかがでしょうか?
この投稿記事では、関西の私鉄の京阪電鉄の石山坂本線(滋賀県大津市内)の沿線の名もない桜の木の画像をアップしてみました。
令和5年1月23日の国会での岸田総理の施政方針演説では「新型コロナ」にも言及がありましたが、私は「ウィズコロナへの移行」が更に進んで、「あらゆる場面で、日常を取り戻すことができる」日が一日も早く来ることを祈っています。
思い切って言えば、参政党の政策として公表されている「新型コロナのモードチェンジ」(注)の実現を望んでいます。
(注)「新型コロナのモードチェンジ…正しい感染症の知識を普及して「コロナ脳」から脱却、国民の行動制限やワクチンに頼らず、日常生活を早く正常化し、免疫力の強化と機動的な医療システム構築でコロナ禍を克服、自由と健康の両立を実現。」(同党のホームページの「新しい国づくり「10の柱」」のうちの「二の柱」の「concept05」より)